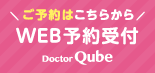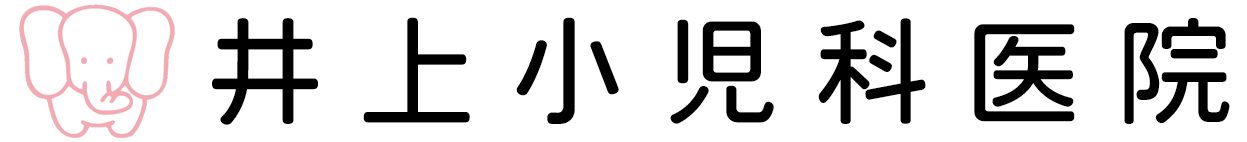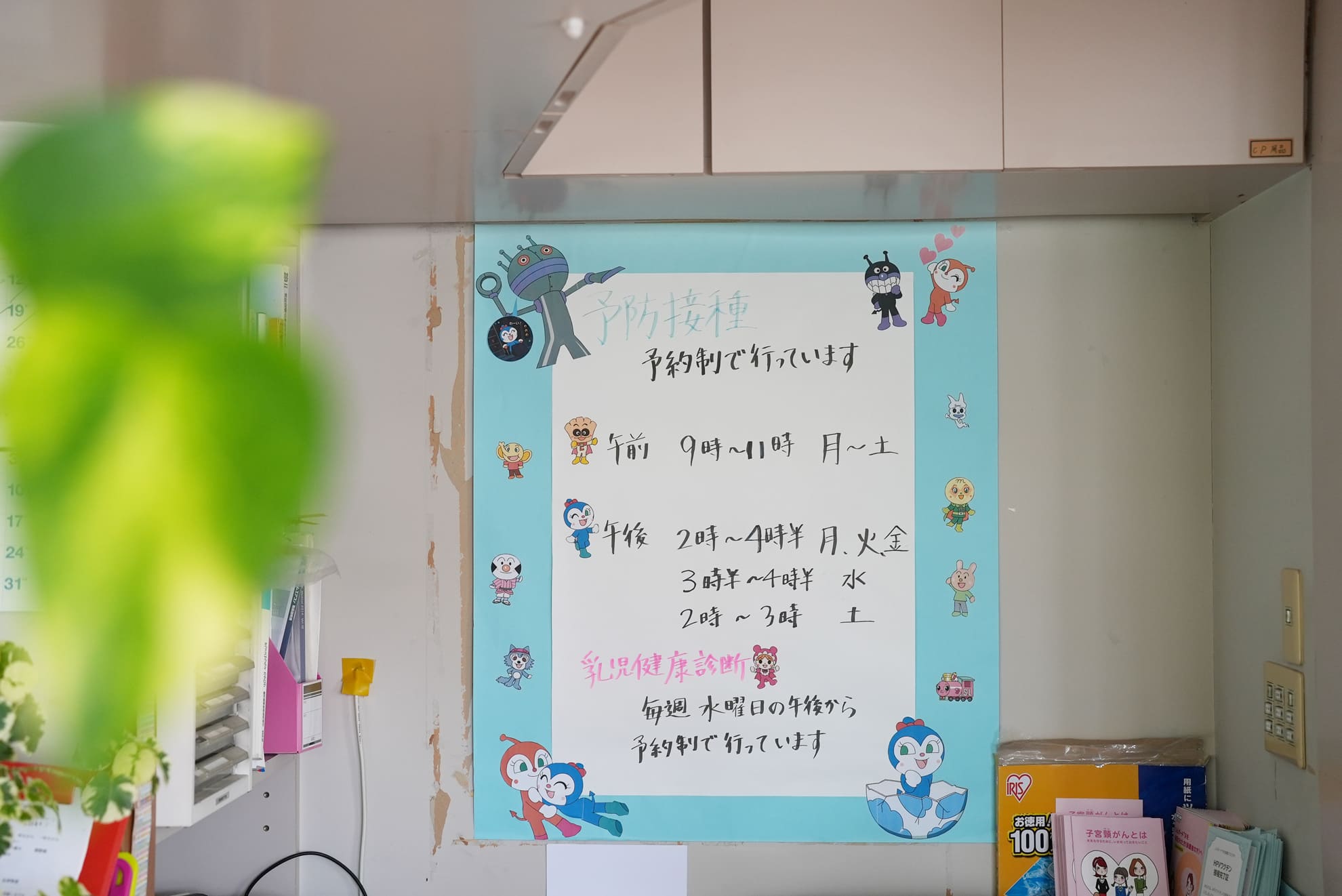お問い合わせはこちらから
アレルギー科
当院では、日本アレルギー学会専門医である院長が、小児のアレルギー疾患に対して専門的な診療を行っています。
アレルギー性疾患は適切な診断と長期的な管理が大切です。
お子さま一人ひとりに合わせた治療と、日常生活に関するきめ細やかなサポートを行い、ご家族と一緒に安心して取り組める医療を目指しています。
以下の疾患や症状に対応しています
- 食物アレルギー
- アナフィラキシー
- アトピー性皮膚炎
- 気管支喘息
- アレルギー性鼻炎(花粉症を含む)
- 蕁麻疹
など
ご相談の多い内容
- 食物アレルギーにおける食事指導や解除のタイミングについて
- アドレナリン自己注射薬「エピペン®」の処方は行なっているか
- アトピー性皮膚炎の塗り薬の使い方と日常のスキンケアについて
- 喘息の発作がでたときの対応と発作予防
- 園や学校での生活に関する書類(生活管理指導表)の作成
など
食物アレルギー
例えば以下のような症状やお悩みがある場合は、お気軽にご相談ください。
離乳食を始める前に、食物アレルギーが出ないか不安に感じている
ピーナッツやナッツ類をまだ食べたことがなく、食べてよいのか心配
果物を食べたときに、喉がいがいがすることがある
など
当院では、診察のうえ必要に応じて血液検査(特異的IgE検査)や皮膚テストを行い、アレルギーの有無やリスクを評価します。
血液検査(特異的IgE検査)では、特定の食物に対する抗体(IgE)の量を調べます。
その際は採血を行い、後日ご説明いたします。
皮膚テストとしては、食材または食品そのものを専用の針で刺し、その同じ針で皮膚を軽く刺激する“プリック・トゥ・プリックテスト(prick-to-prick test)”を行っています。検査後は約15分間皮膚の反応を観察し、腫れや赤みの程度を評価します。
この検査は、血液検査で陽性になりにくいアレルゲンや、血液検査では調べられない食材または食品にも対応可能で、特に果物などの即時型アレルギーの診断に有用です。
※皮膚テストをご希望の場合は事前予約が必要となりますので、事前にお問い合わせください。
また検査を希望する食材または食品については基本的に持参をお願いしております。
なお、これらの検査のみでは「実際に食べられるかどうか」までの判断が難しいことがあります。
その場合には、医師の判断のもとで食物経口負荷試験を行うことがあります。
食物経口負荷試験は、アレルギー正確な診断に加え、除去していた食品が再び食べられるかどうか、またどの程度の量まで摂取可能かを確認するうえで重要な検査です。
当院でも2025年8月より、食物経口負荷試験を院内で実施開始いたします。
※医師の診察・説明の上、完全予約制で行います。
なお、重篤なアレルギー反応が予想される患者様には、提携している二次医療機関(入院・救急対応が可能な病院)での検査をお勧めする場合があります。
安全性を第一に考え、最適な方法をご提案いたします。
乳幼児期に多い鶏卵・牛乳・小麦のアレルギーは、以前は「成長とともに自然に食べられるようになる」と考えられていました。
しかし現在では、皮膚などからのアレルゲン侵入(経皮感作など)を防ぎながら、無理のない範囲で適切に摂取を続けることがアレルギーの改善につながるという考え方(=二重暴露仮説)が広く知られるようになっています。
特にアトピー性皮膚炎などで皮膚バリアが弱いお子さまの場合は、皮膚の炎症をしっかり治療したうえで、原因となる食物を過度に除去しすぎず、適切な量で摂取を継続していくことが大切です。
そのため、どのくらいの量なら安全に摂取できるかどうかを判断するためには、食物経口負荷試験が重要な役割を果たします。
食物アレルギーの診療では、検査結果だけでなく、皮膚の状態や食べられている量なども含めて総合的に評価し、個別に対応していくことが重要です。
また、保育園や幼稚園、学校での給食対応が必要な場合には、「生活管理指導表」の作成にも対応しております。
食物アレルギーに関する不安や疑問がありましたら、どうぞお気軽にご相談ください。
アナフィラキシー
アナフィラキシーは、食物・薬剤・蜂刺されなどが原因で、短時間のうちに全身に強いアレルギー反応があらわれる緊急の状態です。
皮膚の痒みや蕁麻疹、咳、ゼーゼー、腹痛・嘔吐、意識がぼんやりするなどの症状が、急速に進行することがあります。
当院ではアナフィラキシーを起こしたことがある方、またはそのリスクが高いと判断される方に対して、アドレナリン自己注射薬「エピペン®」の処方を行なっています。
エピペン®は、アナフィラキシーが疑われる症状が現れた際に、太ももの外側に注射することで、重篤な状態の進行を一時的に防ぐ薬剤です。処方時には、ご本人や保護者の方へ使用方法を丁寧にご説明いたします。
エピペン®には、体重15kg以上30kg未満の方に使用する0.15mgの規格と、体重30kg以上の方に使用する0.3mgの規格の2種類があります。
そのため、体重15kg以上の方が対象となっており、通常はこの範囲の方に使用されます。
なお、エピペン®には有効期限があるため、1年ごとの更新が必要となります。また、体重が30kg以上となった場合には、エピペン®の規格を変更いたします。
エピペン®の新規処方や更新のご相談も受け付けておりますので、どうぞお気軽にご相談ください。
乳児湿疹・アトピー性皮膚炎
以下のような皮膚の症状でお困りの方は、お気軽にご相談ください。
湿疹がなかなか治らず、よくなってもまたぶり返してしまう
湿疹やかゆみが強く、夜に眠れないことがある
ステロイド外用薬について、使い方や安全性に不安があり、どう使えばよいか知りたい
など
お子さまの皮膚トラブルは成長とともに症状の出方が変わることもありますが、乳児期の湿疹や皮膚バリアの乱れは、将来的に食物アレルギーや気管支喘息などのアレルギー疾患の発症リスクと関係することがわかっています。
そのため、できるだけ早く適切な対応を始めることが大切です。
当院では、皮膚の状態に応じてスキンケアの方法や外用薬(軟膏)の使い方について、丁寧にわかりやすくご説明します。
日常生活の中で無理なく継続できるよう、お子さま一人ひとりに合わせたケアをご提案しています。
外用薬としては、ステロイド外用薬をはじめ、モイゼルト®(デルゴシチニブ)やコレクチム®(ジファミラスト)などの非ステロイド外用薬も症状や部位に応じて使い分けています。
「ステロイドの使い方や安全性が気になっている」「どのように使えばよいか知りたい」といったご相談にも丁寧に対応いたします
また、重症のアトピー性皮膚炎に対しては、外用薬や内服薬に加え、生物学的製剤による注射治療(デュピクセント®〈デュピルマブ〉やミチーガ®〈ネモリズマブ〉)を検討することがあります。これらの治療は、必要に応じて専門的に評価し、ご案内いたします。
皮膚の症状は見た目だけでなく、お子さまの生活の質や睡眠にも大きく影響します。気になることがありましたら、どうぞお早めにご相談ください。
気管支喘息
例えば以下のような症状やお悩みがある場合は、お気軽にご相談ください。
喘息とは診断されていないが、「喘息っぽい」と言われたことがある
咳が長引きやすく、走ったり体を動かすと咳き込むことがある
喘息と診断されているが、毎月のようにゼーゼーしてしまう。
予防薬について相談したい
など
気管支喘息は、乳幼児期にははっきりと診断がつかないことも多く
「咳が長引く」
「ゼーゼーする」
「運動時に咳き込む」
「冷たいものを食べたり飲んだりすると咳がでる」
といった症状を繰り返しているお子さまには、年齢や経過を踏まえた丁寧な評価が必要です。
当院では、アレルギー専門医の立場から、気管支喘息の可能性や治療の必要性について詳しくご説明いたします。
症状の頻度や重症度に応じて、吸入薬を中心とした予防的な治療や、必要に応じて検査を行います。
検査には、呼吸機能検査や呼気中一酸化窒素(FeNO)測定のほか、必要に応じて症状の悪化に関わる可能性のあるアレルゲン(増悪因子)を調べる血液検査を行うこともあります。
呼吸機能検査とFeNO測定は2025年6月から当院でも導入しております。
気管支喘息は、適切な診断と治療により多くの場合しっかりとコントロールが可能です。
「咳が長く続く」「ゼーゼーして眠れない」「運動後に咳き込む」など、気になる症状がありましたら、お早めにご相談ください。
アレルギー性鼻炎(花粉症を含む)
例えば以下のような症状やお悩みがある場合は、お気軽にご相談ください。
春になるとくしゃみや鼻水がひどくなる
寝ているときに目をかゆがったり、鼻づまりで苦しそうにしている
花粉症やダニアレルギーに対して、根本的な治療を受けたいと考えている
など
アレルギー性鼻炎は、花粉やダニ、動物のフケなどさまざまなアレルゲンが原因となります。
鼻水・くしゃみ・鼻づまり・目のかゆみなどの症状が日常生活や睡眠に影響を与えることも多く、的確な診断と治療が重要です。
当院では、症状や生活スタイルに応じて内服薬や点鼻薬による治療に加え、必要に応じてアレルギー検査を行い、原因となるアレルゲンの把握に努めています。
特にスギ花粉症やダニアレルギーに対しては、根本的な体質改善を目指す治療法として「舌下免疫療法」をご提案することがあります。
この治療法は、アレルゲンの含まれる錠剤を1日1回舌の下に置くことで服用し、4〜5年程度継続することで体質の改善を目指すものです。
舌下免疫療法を開始できる年齢として当院では、だいたい5、6歳を目安にしております。
開始にあたっては、ダニやスギ花粉に対するアレルギー(感作)があるかどうかを確認するため、事前に血液検査を行います。
他の医療機関で既に検査を受けている場合は、その結果をご持参いただければ、再検査が不要となることもあります。
なお、初回投与時にはアレルギー反応の有無を確認するため、院内で30分間の経過観察が必要となることから、事前にご予約をお願いしております。
ただし、スギ花粉症に対する舌下免疫療法に使用するシダキュア®は、現在全国的に供給が不安定であり、2025年10月頃までは安定供給の見通しが立っておりません。あらかじめご了承ください。
アレルギー症状にお悩みの方は、日常生活の質を上げるためにも、ぜひ早めにご相談ください。